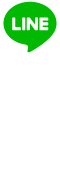群馬生殖医療研究会での講演を通じて:卵子凍結と「選択」のテクノロジー
先週末、第9回群馬生殖医療研究会にて講演の機会をいただきました。大学の先輩でもある、産科婦人科館出張佐藤病院の佐藤雄一院長からのご指名ということで、大変光栄でした。
今回の講演では、私が関わってきた地方自治体との卵子凍結支援プロジェクトについて、そしてその社会的な意味合いについてお話ししました。内容としては、卵子凍結という技術が持つ「選択肢の拡張」という側面に焦点を当てました。
卵子凍結は少子化対策ではない
近年、卵子凍結が少子化対策の文脈で語られることがありますが、私はそれに違和感を覚えています。卵子凍結は、あくまで「女性の活躍支援」や「ライフプランの柔軟化」のための技術であり、妊娠・出産を促すための手段ではありません。妊娠するかどうかは個人の自由であり、社会がそれを強要することは決して許されません。
ワークライフバランスと「全振り」の選択
ワークライフバランスが重要視される一方で、先日誕生した高市総理が「ワークライフバランスを捨てる」という趣旨の発言をされたことが話題になりました。これは一見、時代に逆行するようにも思えますが、何かを成し遂げるために「ワークに全振りする」という選択もまた、尊重されるべきものだと私は考えています。
実際、オバマ前大統領も「人生のある時期には仕事に全力を注ぎ、後にライフで埋め合わせればよい」といった趣旨の発言をされています。この考え方は、現代の多様な生き方を象徴するものでもあります。
妊孕性は「埋め合わせ」がきかない
ただし、妊孕性に関しては「後で埋め合わせる」ことが難しい領域です。卵子の質と量は年齢とともに低下し、時間の制約が厳しく存在します。だからこそ、卵子凍結は「選択肢を未来に残す」ための重要なテクノロジーであり、キャリアとライフのバランスを柔軟に設計する上での支援策となり得ます。
SRHRの視点と知識の普及
もちろん、妊娠を強要することはSRHR(性と生殖に関する健康と権利)の観点からも許されません。しかし同時に、「妊娠できなくなってしまうこと」も避けられるべき事態です。そのためには、卵子凍結を含む妊孕性に関する知識の普及が何より重要です。
今回の講演では、こうした視点を共有し、医療者として、社会の中でどのように「選択肢」を支えていくかを考える機会となりました。
当日乗車した新幹線の写真と、講演の写真を添付しておきます。