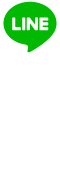生物学的な違いとジェンダーギャップ
このような話題に触れると、時に批判の対象となるかもしれません。ですが今回は、不妊治療の現場に身を置く者として、日々感じていることを率直に綴ってみたいと思います。
まず大前提として、性別による差別や役割の強制は決して許されるべきではありません。しかし、妊娠・出産に関しては、生物学的に男女の役割に明確な違いがあることもまた事実です。子どもを持つかどうか、いつ、何人持つかという選択は人権の一部であり、尊重されるべきものです。ただし、その選択には生物学的な限界が伴い、性別による違いは避けられません。
ここで、「平等(Equality)」と「公平(Equity)」という概念について考えてみたいと思います。
• 平等とは、すべての人に同じ条件・資源・機会を与えること。出発点が同じであることを前提としています。
• 公平とは、個々の状況やニーズに応じて、適切な支援や資源を提供すること。出発点の違いを認識し、それを補うことが目的です。
たとえば、スポーツの分野では体力的な差を前提に男女別の枠が設けられており、これは公平の考え方に基づいています。妊娠・出産においても、女性に大きな身体的・時間的負担がかかることは明白であり、さらに妊娠可能な年齢には限界があります。こうした現実を踏まえれば、制度や支援の設計において公平の視点が不可欠です。
しかしながら、妊娠する・しないは個人の選択であり、性教育が不十分なままでは、その選択を支える公平な環境が整いません。これは、現在の日本における少子化の一因とも考えられるのではないでしょうか。
もちろん、子どもを持つことを強制するような発想は論外です。ただ、子どもを望む気持ちさえも口にしづらいような社会的空気があるとすれば、それは非常に憂慮すべきことです。
特に、旧来の価値観を持つ比較的高齢の男性には、こうした現実が実感しづらいかもしれません。そして、そのような方々が社会や企業の意思決定層に多く存在していることも、構造的な課題の一つです。性教育の不十分さが、こうしたギャップをさらに広げているように感じます。
私は医療従事者として、不妊治療の現場から社会に問いかけ、変化を促すことも使命のひとつだと考えています。今後、さまざまなメディアを通じて発信する機会があるかもしれませんが、どうか温かく見守っていただければ幸いです。