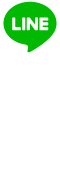命を継ぐということ──『鬼滅の刃』の感想
先日、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を観に行ってきました。公開からわずか10日間で興行収入128億円、観客動員910万人を突破した記録的ヒット作。休日だったこともあり、劇場は満席。世代を超えて多くの人々がこの作品に心を寄せているのだと、改めて実感しました。
スクリーンに映し出されたのは、命を削って戦う人間たちと、死を拒む鬼との壮絶な戦い。ネタバレになるかもしれませんが、猗窩座は愛する者を守れなかった過去に苦しみ、鬼になることで永遠の命を得て、さらに強くなろうとします──ある意味で、崇高な存在といえるかもしれません。
その猗窩座に立ち向かう炭治郎たちの姿を見ながら、ふと考えさせられました。
「人間は弱い。でも、技を継げるし、命を繋げる。」
たしかに弟子に裏切られることもあるかもしれません。しかし、寿命を持つ人間だからこそ、次の世代を信じ、託すという行為が意味を持つのでしょう。この言葉には、物語を貫くテーマだけでなく、現代社会への深いメッセージが込められているように感じました。
少子化時代における“継承”の意味
日本をはじめとする先進国では、少子化が深刻な社会課題となっています。経済的負担やライフスタイルの変化により、出産や育児は「選択のひとつ」となりつつあります。
しかし、子どもを育てることは単なる生物学的な再生産ではありません。OECDの報告によれば、育児は子どもの認知・情緒・社会性の発達に決定的な影響を与え、文化・技能・価値の継承でもあるのです。
さらに、2024年に発表されたLindahl-Jacobsenらの研究によると、妊娠までの期間が長かった親ほど、平均寿命が短い傾向にあることが示されています。これは「妊娠・育児」にもタイミングがあることを示唆しており、現代社会において見過ごすべきではない知見です。
技術を継ぐ、もうひとつの道
もちろん、すべての人が子どもを持てるわけではありません。そして、子がいなくとも、人は何かを“遺す”ことができます。
その代表例が師弟関係やメンターシップ。米国の研究では、メンターは単なる技術の指導者ではなく、「価値観」や「人間性」を継承する存在だとされています。『鬼滅の刃』における柱と継子の関係は、まさにその象徴でしょう。
経済学者James Heckmanの研究によれば、家庭や師弟関係を通じた技能の継承は、学校教育を凌ぐほどの影響力を持つ可能性があるとも指摘されています。
命ある時間に、何を遺すか
『鬼滅の刃』は、死と向き合う物語であると同時に、「生きている間に何ができるか」を問いかける作品でもあります。それは、私たち現代人にとって、社会的にも倫理的にも根源的なテーマです。
命を育てること。
技を鍛え、継ぐこと。
想いを受け継ぎ、伝えていくこと。
それらはすべて、人間が“弱さ”のなかで選び取ることのできる、尊い力。――そしてそれこそが、「鬼にはできないこと」なのかもしれません。
そして、現代に生きる私たちはどうでしょうか。寿命が延びたことで、「今をいかに充実させるか」に意識が向かい、現世であらゆる体験や成功を求める思いが強まっているように感じます。自己実現や物的豊かさを追い求めるあまり、時に「我利我利亡者」のように、欲望が際限なく膨らんでしまう現代人。
その姿は、まさに物語に登場する鬼の象徴なのかもしれません。死を拒絶し、永遠を求めて彷徨う鬼の姿は、有限性を受け入れられない現代社会の鏡像として、私たちに鋭い問いを投げかけているのです。
おわりに
命に限りがあるからこそ、「何を継ぐか」を真剣に考える――それが、現代における“生きる力”につながるのではないでしょうか。
子を育てることも、弟子に技を伝えることも、いずれも“継承”という尊い営みです。
少子化の時代だからこそ、私たちはあらためて、「命のバトン」の重みを見つめ直す必要があるのかもしれません。