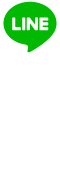午前3時の総理と当直明けの執刀医──制度疲労が生む“働きすぎ”の構造
2025年11月、高市早苗総理が「午前3時に公邸で答弁書を確認していた」と報じられ、SNS上では驚きと疑問の声が広がりました。この背景には、国会質問通告の遅延という“慣例”が存在しています。質問通告は本来、委員会開催の2日前正午までに行うべきとされていますが、実際には前日夕方から夜にかけてずれ込むことが多く、官僚たちは深夜に答弁書を作成し、総理や閣僚は早朝にチェックするという非人間的なスケジュールが常態化しているのです。
私自身、大学時代の知人が厚生労働省に出向していたことがあり、数年前にその実態を聞いたことがあります。国会開催中は、深夜まで答弁準備に追われ、朝方に霞が関を出ることも珍しくなかったそうです。周囲にはタクシーが待機していて、それで帰宅することはできるものの、数時間後には再び出勤しなければならず、極めて過酷な労働環境だったと語っていました。こうした働き方が“日常茶飯事”であることに、当時も驚きを覚えましたが、令和の今もなお改善されていないことには、働き方改革とは何だったのかと首をかしげてしまいます。
この構造は、医療現場の「当直明けの手術」とも共通しています。医師が夜間当直を終えた直後に手術を行うことは、疲労による判断力の低下を招き、患者の安全に影響を及ぼす可能性があります。私自身も医療者として、当直明けに執刀することは当然のようにありましたし、そのまま再度当直に入ることも多く、さらには学会や講演会への出席も重なり、休む間もなく働いていた時期がありました。使命感や責任感が支えていたとはいえ、制度として持続可能だったかと問われれば、疑問を感じざるを得ません。
国会と医療──“準備の質”が成果を左右する職種です
国会答弁も医療手術も、準備の質が結果に直結します。疲弊した状態での議論や執刀は、制度の信頼性を損なうことにつながります。高市総理の「午前3時出勤」は、単なる個人の働きぶりではなく、制度疲労の象徴であるといえるでしょう。質問通告の遅延は、官僚の過重労働を生み、政策の質にも影響を与えます。医療現場でも、当直明けの執刀が医療安全を脅かします。いずれも「慣例だから」「仕方ないから」と放置するのではなく、制度設計の見直しが求められています。
慣例を壊す勇気──制度の持続可能性のために
働き方改革が叫ばれる令和の時代において、制度疲労を放置することは、職業倫理にも反すると考えます。国会では質問通告のデジタル化や期限厳守、医療現場では勤務間インターバルの徹底など、すでに改善策は議論されています。問題は、それを“実行する勇気”です。
「午前3時の総理」と「当直明けの執刀医」は、制度の限界を超えて働く姿の象徴です。しかし、使命感だけでは制度は持続しません。人間らしい働き方を前提とした制度設計こそが、良質な議論と安全な医療を支えるのではないでしょうか。