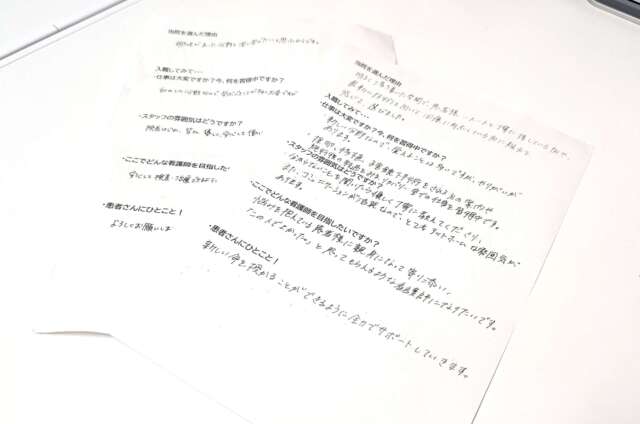養成講座に参加して感じたこと
「養成講座」という言葉には少々堅苦しい印象を持つ方もいるかもしれませんが、今回は先日、不妊カウンセリング学会主催の不妊カウンセラー養成講座に出席した際の経験についてお話しします。この講座は年に2回開催されており、私は定期的に講師を務めるだけでなく、座長として司会も担当しています。
私が担当する内容は、ほぼ毎回同じく「不妊治療の基礎知識」に関する講義です。保険適用が開始されてから3年以上が経過しましたが、基本的な不妊治療の知識とその背景について改めてお話しさせていただいています。講義は会場の受講者だけでなく、WEB配信や学会会員向けのアーカイブ視聴も可能となっており、多くの方々に学んでいただける機会となっています。
この養成講座は、不妊カウンセラーの認定取得に必要な講義ですが、単に治療に関する知識だけでなく、治療当事者の声や考えさせられるテーマを含む内容が盛り込まれています。今回座長を務めさせていただいた講義では、順天堂浦安病院時代に大変お世話になった泌尿器科の辻村先生による「男性不妊」についてのお話でした。久しぶりに辻村先生とお会いする機会があり、嬉しくてインスタグラムにも写真を投稿しました。
また、せっかく現地に足を運んだこともあり、いくつかの講義を途中まで拝聴しました。その中でも特に印象的だったのが、根津八紘先生のお話です。根津先生は、日本産科婦人科学会が禁止している卵子提供や代理母による治療を行い、一時学会から除名された経歴を持つ方です。講義では「妊娠障碍者」への支援の必要性について、現代国家が障碍者を支援する以上、「妊娠障碍者」も配偶子提供や代理母を通じた支援を受けるべきだ、というお考えを述べられました。
生殖補助医療法案が国会に提出されている今だからこそ、親子のあり方や子供を持つ意義について考える必要があると感じます。我が国では性教育が十分に機能していない現状もあり、この議論が進むには時間を要するかもしれません。しかし、これは国民全体で向き合うべき重要なテーマだと痛感しています。